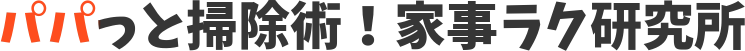忙しい日々の中で、「どうすればもっと家をスッキリさせられるのか?」と悩むことが多く、特に収納に関しては試行錯誤を重ねてきました。以前は片付けを一人で頑張っていたのですが、せっかく整理しても家族がすぐに散らかしてしまい、ストレスが溜まるばかりでした。そこで、「収納ルールを家族全員で共有すれば、もっとスムーズにいくのでは?」と考え、試してみたのです。
家族で収納ルールを話し合うことの大切さ
まず、家族みんなで収納について話し合う時間を作りました。この話し合いでは、「どこに何をしまうか」を家族全員で決めることを目的としています。私が一方的にルールを決めるのではなく、夫や息子の意見を聞きながら決めることで、みんなが納得できる収納ルールを作ることができました。
例えば、夫は仕事から帰宅するとカバンをソファに放置しがちだったので、「玄関近くにカバンを置けるスペースを作ったら?」と提案。息子も学校の準備がしやすいように、ランドセルを置く定位置を一緒に決めることで、「ここに置けばいいんだ」と理解し、自然と片付ける習慣がつくようになりました。
収納スペースを家族ごとに分ける工夫
収納スペースを家族ごとに分けることで、それぞれが自分のものを管理しやすくなります。私は家のクローゼットや引き出しを見直し、夫専用、息子専用、私専用の収納スペースを確保したのです。これにより、「これはどこ?」と聞かれる回数がぐっと減りました。
息子の収納は、彼が自分で片付けられるように低い場所に配置し、ラベルを貼って中身がわかるようにしています。ラベルによって何がどこにあるのかが一目で分かるようになり、物を探す時間が短縮されました。
視覚的に分かりやすい収納の工夫
収納のルールを作っても、守らなくては意味がありません。そこで、「見てすぐ分かる」ようにラベリングを活用しました。引き出しや棚に「文房具」「救急箱」「おもちゃ」などと書かれたラベルを貼ることで、夫や息子が「ママ、どこにある?」と聞くことが減り、自然と自分で探して使うようになったのです。
さらに、収納の色分けも取り入れました。息子のものは青、夫のものは黒、私のものはピンクと色を決めることで、一目で自分のものがどこにあるかが分かり、探しやすくなりました。
使う頻度を基準にした収納の配置
収納を決める際には、「使う頻度」を基準にすることも重要です。毎日使うものはすぐに手に取れる場所に置き、週に1回使うものは取り出しやすい場所へ、年に数回しか使わないものは奥のスペースへ収納するようにしました。
玄関の靴収納には、よく履く靴だけを並べるようにし、あまり使わない靴は別の場所に片付けることで、毎朝の「靴が見つからない!」というプチストレスが解消。キッチンでも同じで、調味料はすぐ手に取れる場所に並べ、あまり使わないものは奥に収納することで、料理の時間が短縮されました。
収納ルールの定期的な見直しとアップデート
収納ルールは一度決めたら終わりではなく、定期的に見直すことが大切です。我が家では、「シーズンごとに収納を見直す」というルールを作り、家族の成長や生活スタイルの変化に応じてアップデートするようにしました。
息子が遊ばなくなったおもちゃを片付けるタイミングや、夫が新しい趣味を始めて増えた道具をどこに収納するかを話し合うことで、常に適切な収納環境を維持できるようになりました。
家族で共有する収納ルールを実践してみて
このように、収納ルールを家族みんなで共有することで、家の中がすっきりし、片付けにかかる時間が大幅に短縮。以前は「片付けて!」と何度も言わなければならなかったのが、今では自然とみんなが片付ける習慣がつき、私の負担も減りました。収納は一人で頑張るものではなく、家族全員で考え、共有するものだということを実感したのです。
もし、「片付けがうまくいかない…」と感じているなら、ぜひ家族みんなで収納ルールを見直してみてくださいね。